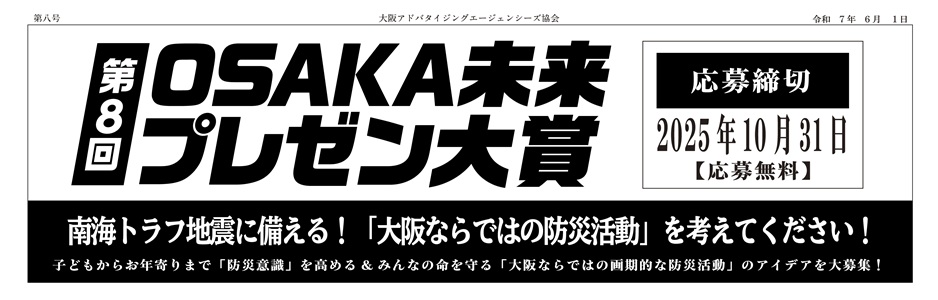第43回 OAAAクリエイティブ研究会
「2023年クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞 受賞者講演」
第43回OAAAクリエイティブ研究会は、2024年10月23日(水)に、大阪大学中之島センターにて、92名の参加者を前にリアルな形で開催した。昨年度に引き続き、当協会と日本広告業協会との共催で、2023年クリエイター・オブ・ザ・イヤーを受賞された高崎氏、メダリストを受賞された有元氏、松尾氏のそれぞれの視点から大いに語って頂いた。クリエイターの生の声をリアルな会場に参加して聞くことのできる講演会は大変好評をいただいた。
第1部:2023年クリエイター・オブ・ザ・イヤー メダリスト
九州博報堂 クリエイティブ局 コピーライター
松尾 昇氏

地方で広告をつくる僕たちのひとつの勝ち筋
■土用の丑の日問題
福岡での仕事は常に予算が限られています。そんな中でも注目を集めた事例を今日は紹介したいと思います。1つ目は、鹿児島県鹿屋市のシティプロモーションの事例です。鹿屋市が誇る市の二大名産品、鰻と和牛を、ふるさと納税を意識しつつ全国の方にPRするというもので、予算は2千万円あまり。鰻も和牛も全国にライバルが数多く存在するので、真っ向勝負では効果は望めません。そこで土用の丑の日に着目しました。そもそも丑の日にうのつく食べ物「鰻」を食べるという説は、ロジックとしても弱く、ツッコミどころがあるなと感じていました。そこで鰻と牛どちらを食べるべきか、「土用の丑の日問題」として生産者同士が論争を繰り広げる新聞広告を掲載し、ウェブ広告には、鹿屋市のクリエイティブ・ディレクターを任されているお笑い芸人のサンシャイン池崎さんも出演頂きました。Xを起点に反響が広がり、ちょうど夏場だったのでメディアでも多く取り上げられ、地場産業の活性化に貢献することができました。
■ダイショー
次は福岡の食品メーカー・ダイショーの事例です。2020年に地元では有名な焼き肉のタレを全国に向けてプロモーションする仕事に初めて携わりました。大手メーカーが強いこの市場に参入していくので、ウェブでホームランを狙っていくしかないと考え、候補になったのが地元出身のお笑い芸人、なかやまきんに君です。以前から過小評価され過ぎでは?と感じるほど注目していて、担当者も大ファンだったことから、彼のギャグを生かした動画を制作し、「パワー!」と叫ぶだけの謎の広告がスキップボタンを押せない状況を作り、Xなどで広く拡散されて話題になり、売上も伸長しました。
翌年は鍋スープのプロモーションを企画。今回もなかやまきんに君を起用し、前回同様ウェブで爆発するパターンが求められました。鍋のCMといえばほっこり家族がお決まりだが何か嘘くさい。そんな家族に説明もなしになかやまきんに君を放り込むことで異質なアプローチができるのではないかと思い、結果こちらもX上などで拡散され、話題となりました。
■アビスパ2万人プロジェクト
最後は地元のサッカークラブ・アビスパ福岡のプロモーションです。地元には超人気球団ソフトバンクホークスがいるせいか、何度もJ2に降格しているサッカーチームのアビスパは存在感が薄く、ファン獲得に伸び悩んでいました。しかし2023年はJ1で8位、天皇杯でも4位と大健闘し、そこで「アビスパ史上、今が一番おもしろい」というスローガンの下、アビスパ2万人プロジェクトを始動。J1リーグ第31節vs横浜マリノス戦に向け、スタジアムを満員(2万人)にするという目標を掲げて、プロモーションを実施しました。
目玉となった企画がアビスパトレインで、福岡市地下鉄6両1編成を丸ごとジャックしました。ポスター制作にあたっては、Jリーグにもアビスパにも興味がない人たちにただかっこいい広告をやっても効果は望めないと考え、「愛犬が懐いてくれない」「小学校の頃から同じ美容室に通っている」など、選手の人柄が伝わるような一言を入れ、興味の入口にしました。地元のテレビ局にも取り上げてもらって話題を拡散しました。なかやまきんに君が広報活動をサポートしてくれ、スタジアムでのパワー斉唱も注目を集めました。結果的に2万人には届きませんでしたが、動員数は155%増となりました。その後物語は続き、YBCルヴァンカップでは悲願の初優勝。前日には選手たちを送り出す新聞広告を掲載し、多くの福岡県民の注目を集めることができ、博多駅での優勝報告会には以前では考えられないほどのファンで埋め尽くされました。

こうした反響のあった広告を振り返ってみると、共通しているのは「個人的な感覚×クライアントの勇気」だなと思います。土用の丑の日のロジック、弱くない?なかやまきんに君、過小評価され過ぎてない?鍋の広告に出る家族ってなんか嘘くさくない?スポーツのかっこつけ広告って寒くない?といった個人としての感覚のまま、あまりかしこまり過ぎずに広告をつくる。それはたくさんのチェックを経た広告と違うものになりやすいし、本音でつくっているぶん、無視されがちなきれいごとにはなりにくい。勇気があるクライアント(担当者)がいる時点でけっこう勝ちゲームなんだと思います。眼の前のクライアントと良い関係が築ければ、地方の場合なんとかなります。クライアントと仲良くなること、信じてもらうことが僕達の仕事の大部分で、それが地方で広告をつくる僕達の勝ち筋なのかも、と思います。
第2部:2023年 クリエイター・オブ・ザ・イヤー メダリスト
電通 zero クリエイティブディレクター/コピーライター
有元 沙矢香 氏

ファンと共創する広告
■「君の名は。」地上波プロモーション
昔から大のお笑いファンだった私が、広告に興味を持ったのはあるCMがきっかけでした。それはホットペッパー「居酒屋クーポン」のCMで、15秒で人を惹きつけて笑わせる広告の力に魅了され、どんどん広告の世界にはまっていきました。入社後はサントリーやJR九州などいろいろと良い経験を積ませていただき、転機となった仕事が「君の名は。」です。
これは映画の地上波放送を盛り上げたいという媒体局からのオーダーです。大ヒット映画なので、ターゲットはすでに映画を観たことのある人。それを配信ではなく、地上波で見てもらうためには、みんなで同時に見る“体験”を作ることが大事だと思い、そこで地上波特有の“視聴体験”を作るため、Xで盛り上がる企画を考えました。
例えば番宣としてテレビ朝日の深夜番組「全力坂」を活用し、ヒロインが坂を走るシーンをつなぎ合わせて、登場させました。放送当日の新聞広告には、主人公2人の物語の重要なシーンが自分の手で再現できる仕掛けを作りました。提供表示が入れ替わるテレビ史上初の試みや、ABEMAやXで生副音声の番組を行うなど、映画館では体験できない楽しみ方を提供することで、地上波放送を盛り上げることに成功しました。
テレビ局の宣伝費には限りがあり、営業も媒体担当で慣れていないため、実現に向けては自身も奔走しました。そこで、(表現の)アイデア以外にもアイデアを使う大切さを実感しました。クライアントが持つ資産を活用したり、提案の仕方を工夫したり。そもそも、放送を盛り上げる目的は、視聴率を上げ、枠の価値を高めるためで、媒体の価値を高めるための広告として、媒体資料で提案することで、各スポンサーさんにご納得いただくことができました。ラテ局のビジネスモデルや、テレビ局の提供ルールなど、学ぶことで解決するためのアイデアを考えられます。そして、結局、企画を実現するのは「人」です。その人と話し、その人の抱える課題を一緒に解決することが実現に向けての鍵となります。私はあまりロジカルではないので、企画書を書くことが苦手でしたが、企画書はロジック以上にニーズだということを学びました。そして何よりファンのパワーを実感しました。反響は海外にまで広がり、コンテンツの仕事はファンの分析と理解が非常に大事だと感じました。
■M-1グランプリ
この経験を経て2018年、M-1グランプリに携わることになりました。若い人のテレビ離れもあり、当時視聴率は伸び悩んでおり、ちょうどTikTokがサービスを開始した時期だったので、TikTokのいろんな機能を使ってプロモーションを実施しました。結果的にその年のM1・F1層の視聴率が上がり、2019年から大会全体のプロモーションに携われることになりました。本番に先駆け、六本木駅構内では歴代王者のポスター展を開催し、各年優勝者のM-1に対する想いを表すポスターを掲出しました。掲出期間がM-1翌日までだったので、最後の1枚を白紙にし、決勝後すぐに新王者にインタビューと撮影を行い、明け方貼り替えました。
2020年はコロナのため予選は無観客で実施し、決勝戦だけお客さんを入れました。そんな状況でもエントリーしてくれた漫才師の方々へエールを送りたく、全員のコンビ名を入れたポスターを新宿駅などで掲出し、この年から予選の密着映像を使用したプロモーションビデオの制作も始めました。
2021年以降は前年王者のマジカルラブリー、錦鯉、ウエストランドをそれぞれキービジュアルに起用し、ファンの皆さんに反応してもらえるよう、芸人さんのキャラクターやネタを活かした広告作りに励みました。出場される漫才師の方々も毎年注目してくださり、ファン、漫才師、制作チームが一緒になってM-1というお祭りを盛り上げているという実感が湧きました。
M-1のプロモーションは毎年夏頃にオリエンがあります。プロデューサーさんの想いを伺い、その年のテーマとなる言葉をまずは開発します。その後、Xでファンの気持ちや世の中の温度感、参加される芸人さんの気持ちなどを徹底的にリサーチし、企画に入っていきます。
去年のメインポスターは、「爆笑が、爆発する。」というキャッチコピーです。司会の今田耕司さんが番組中に何度か言われていた「まだ爆発が起きませんね〜」という言葉と、ストイックに漫才と向き合いたいという番組の意向を融合させ、ヒリヒリする感じを表現しました。
メインポスターが決まると、このコンセプトがスタジオのセットや演出にも反映されていきます。一方、プロモーションは話題化を狙うため、ウエストランドがどういうことをするとファンの人が一番楽しんでくれるかを考えました。決勝当日のクリスマスイブに井口さんが毒を吐く駅貼り広告、敗者復活戦が初めて屋内で行われることを知らせる号外広告、関西では阪神優勝に便乗したアレ広告、視聴率が最も高かった青森県への感謝広告など、昨年も様々な展開を行いました。
 プロモーションビデオは、毎年ファンの方がとても楽しみにしてくださっている分プレッシャーも大きいです。漫才の制限時間と同じ4分に、ファンの方に喜んでもらえるディティールを詰め込みまくることで何度も観たくなる映像を目指しています。約30台のカメラで追った何百時間という素材を編集する大変な作業ですが、コメント欄への多くの反応やYouTubeの急上昇ランキング1位など、うれしい評価が励みになっています。PVを始めた当初はオリジナル楽曲も考えていましたが、既存曲の中にもM-1戦士の心情にぴったりな隠れた名曲があることに気づき、その年のテーマや気分に沿った最適な曲を厳選しています。
プロモーションビデオは、毎年ファンの方がとても楽しみにしてくださっている分プレッシャーも大きいです。漫才の制限時間と同じ4分に、ファンの方に喜んでもらえるディティールを詰め込みまくることで何度も観たくなる映像を目指しています。約30台のカメラで追った何百時間という素材を編集する大変な作業ですが、コメント欄への多くの反応やYouTubeの急上昇ランキング1位など、うれしい評価が励みになっています。PVを始めた当初はオリジナル楽曲も考えていましたが、既存曲の中にもM-1戦士の心情にぴったりな隠れた名曲があることに気づき、その年のテーマや気分に沿った最適な曲を厳選しています。
芸人さん、運営、ファンの方々が一体となった盛り上げの結果、配信数や視聴率の上昇にもつながっていることは大変嬉しく、なにより、エントリー数が4094組(2017)から10330組(2024)に増加したことは本当にありがたいことだと感じています。
コンテンツ過多な時代。広告しすぎていると見てもらえない。①ファンの心情を深く知り、②どんな媒体でも体験に変えるようなアイデアを考え、③コンテンツの魅力を最大化する。これまでのコンテンツの仕事を通じて、コンテンツを一緒に育てていくために広告は、そのコンテンツを深く愛する制作者、そしてファンの方を尊重し、彼らが愛するその魅力を一緒に育てていくことが大切だと学びました。
第3部:2023年 クリエイター・オブ・ザ・イヤー
dentsu Japan/電通コーポレートワン グロースオフィサー
エグゼクティブ・クリエイティブディレクター
高崎 卓馬 氏

広告のこれから
■×3の鉄則
この業界にはいって30年ほど経ちますが、若い頃に感じていた悩みや壁というものはまったくなくなっていません。よくいつこの苦しさから抜けられるかと聞かれるのですが残念ながら。自分のスキルがあがると、仕事の責任も増えるし、期待値もあがる。それに応えるには企画の段階で苦しんでおくしか方法はないんです。自分がいい仕事をしていると決まって、後輩たちから「あれどうやって作ったんですか?」という質問がきます。「いいですね」とか「好きです」とかよりもその質問がきたときはいい仕事になっているんだと感じます。オリジナリティのあるものになっているという証明だと思います。
最近、後輩や仲間たちによく言っているのがこの「×3の鉄則」です。これは来た仕事を必ず3倍にしてしまうというもので、オリエンに応えるだけじゃなく、その仕事をきっかけに頼まれてもいない仕事をつくる意識をもつということです。オリエンに応えているだけでは想像を超えた仕事は絶対につくれません。そして本当にクライアントや世の中が求めているものは生まれません。クライアントも、オリエンはしているがそれをこなせば必ず結果がでると確信をもっているわけではありません。そこには悩みが書いてあり、それを解決するクリエイティブは実は無限にあるはずです。自分が今このタイミングでその仕事をすることになったその理由は、今の自分にしかできない何かが求められているからで、それを探るためにも、自分の意識を拡大する意味でも、強制的に発想を×3倍にするというのはとても効果的だと思います。
■広告の限界、アートの可能性
「PERFECTDAYS」という映画をつくりました。監督はドイツ人のヴィム・ヴェンダースさんです。この映画のすべてのきっかけになったのが、渋谷の公共トイレを作り直す「THE TOKYO TOILET」というプロジェクトです。これは柳井康治さん(ファーストリテイリング取締役)が個人で企画から資金調達までやって実現したもので、暗くて汚くて臭いイメージの公共トイレを生まれ変わらせようという取り組みです。このプロジェクトを進めていた柳井さんが僕にある相談にこられたんです。具体的な予算があって、ミッションがあって、というものではなく、自分のやっているこのプロジェクトをどう思うか?という雑談に近いもので。その会話のなかで、このプロジェクトの課題や、将来のことをかなり自由に会話しました。そしてそれを1週間おきくらいに定期的につづけました。何かゴールがあってということではなく、何が問題か、何が今起きているのか、なんで自分たちはそう感じるのか。そんなことを丁寧に会話しました。その贅沢な時間があったからのちにこういう映画が生まれる土壌になったのだと思います。
トイレの最大の課題はメンテナンスです。でもそれを広告の手法、PR的な方法で世の中に伝えるということにどうしても違和感がありました。その主な理由は、広告はそれがあるときは効果があるかもしれないが、それが消えたときにはまた元にもどってしまうという広告の宿命みたいなものだったり。あるいはそれをそんなに真剣に考えず、広告として目立って褒められるものをつくるために「課題探し」だけして、その課題が本当に解決したかまでは責任をもたないなんとなく僕をふくめ広告の業界のもっている軽さのようなものだったりしました。そのことを柳井さんとも話をして、このプロジェクトでは広告的なアプローチはしないと決めました。そのときジョンマエダさんの言葉を柳井さんが教えてくれました。
「デザインは課題を解決するが、アートはみんなに課題を共有する」。というようなことだったと思います。これが大きな啓示をくれました。デザインではなく、アート。それがのちの背骨になったのです。それからアートを軸にしたいろんなアイデアを考えていくうちに映画という発想になったのです。この映画の生まれた背景は、リトルモアという出版社からでている「逆光」という本にほとんどのことを書きました。ぜひ興味のある方は読んでみてください。
ヴェンダースの映画は、自分をこの世界にいれた大きなきっかけでした。彼の映画に出会い自主映画をはじめ、そして今にいたります。そんな自分の原点にいるひとと一緒に映画をつくれるというのはこれ以上ないごほうびでもあり、同時に好きなひとに嫌われたくないので、異常なプレッシャーのなかの作業でした。
この映画は主演の役所広司さんの演技がすべて、ともいえます。ヴェンダース監督にオファーするときに、トイレ清掃員を主人公にするということだけ決めて、その役を役所さんにオファーに行きました。けれど脚本もないし、映画会社もいない。なかなか訳のわからない失礼なオファーだと自分でも思います。できることはそんなにないので、ひとまず、トイレ清掃を経験しました。まだ暗い朝から1日中、膝をついて、たくさんの公衆トイレを掃除しました。そのとき清掃の指導をしてくださった江田さんという方が、その背中でたくさんのことを教えてくださいました。まるで修行する僧侶のようだ。究極の利他の生き方がここにあると猛烈に感動しました。そしてそれまで自分は見ているようで見ていなかったことを反省しました。世界に対する気づきがありました。この気づきは役所さんとお話しするときも、監督にオファーするときも、それから映画をつくりあげていくときも大きな最初の起点になった気がします。監督にそのことを伝えたとき「トイレは人種や貧富に関係なく、全ての人にとっての小さな聖域かもしれない」と言われました。
■映像の使命、物語の使命
それから東京でシナリオハンティングをし、ベルリンで脚本づくりをし、撮影も編集もすべてのプロセスをともにしました。日本人が日本で演技するものをドイツ人が監督するので、日本人がみて違和感のないものにするために、必ず自分の横にいるようにと言われました。これは本当に特等席でした。映画づくりの最前線で、その悩みも喜びもすべてわかちあいながらやりました。映画とCMは根本的に別のものです。同じように考えてつくってはいけません。映画は100人がみて100人が違う感想をもつべきものです。CMはそこにあまり誤差がないようにする。その違いを考えてつくらなければCMみたいな映画という作る意味のないものしか生まれません。ただ映像という言語という意味では激しく共通することがありました。映像を言語として、その仕組みやその意味を考えつづけてCMをやってきたおかげで、本当に細かいクラフトの部分が通用しました。これは本当にうれしかった。いっしょに今までやってきた、僕にたくさんのことを教えてくれたCMの演出家たちの名前を心のなかで何度か叫びました。
編集で2時間ほどになったときに、「これはいいものができそうだ。どうやって公開する?」と監督に聞かれて初めて、公開する方法を考えていなかったことに気づきました。そこまで無我夢中だったのです。それから海外の映画関係者を仲間にして映画の公開の旅がはじまりました。新しい仲間たちがカンヌ映画祭に出品するべきだと強く進言してくれたおかげで、アカデミー賞のノミネートまで奇跡のような経験ができました。映画は世界90カ国ほど公開になり、監督のキャリアで一番お客さんのはいった映画になりました。こんなにうれしいことはありません。
■なんで?と疑う、2回企画書を書く。

ゴールを決めて仕事をすると、それ以上のものにはならない。そう思います。起きている出来事や環境の変化にあわせて常に最適な解を考えトライ&エラーをくりかえす。そうしていくと雪だるまは大きく遠くまで転がっていきます。強いアイデアを生む考えかたの基本原則は常に、どんなことでも「なんで?」と立ち止まり、その背後にあるものを考えて「だったら」と答えを探していくことです。それをくりかえすとオリジナリティのあるものに到達します。人がやっていないものになる。
あと、本当に具体的なアドバイスなのですが、企画書は2回書くといいと思います。1回目は自分の企画をつくるための思考の整理のため。それでストライクゾーンを外していないか確認する。そして具体案ができたら、それをクライアントがやりたくなるような話し方を考えてその説明を魅力的にするための企画書を書く。決して自分の考えたプロセスを企画書にしない。これはとても大事で、今すぐにでもみなさんの企画が通りやすくなる秘訣なのでぜひ、お試しください。