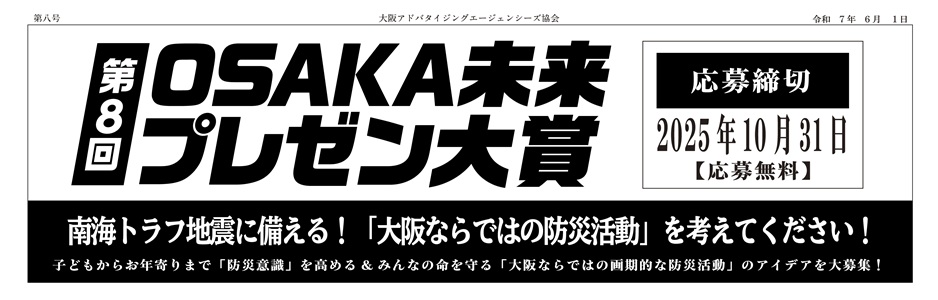第14回 OAAA人権セミナー

第14回目を迎えるOAAA人権セミナーは、昨年同様にオンラインセミナーの形をとって2024年11月21日(木)に開催した。今回のテーマは、3年に一度はテーマとして取り上げることとしている部落問題について。そもそも部落問題とはいかなる社会問題であるのかを入門的に学ぶ機会として、差別が生じるメカニズムや、部落問題の歴史的な概説、理解のために必要な用語解説など、関西大学 社会学部 教授で、堺市人権施策推進審議会委員の会長も務められている内田 龍史様にご講演頂いた。広告業界においても「人権」の観点の重要性がますます高まっている中であり、前回を上回る73名の参加登録があった。
テーマ/ 「部落問題のこれまでとこれから」
講師 / 内田 龍史(うちだ りゅうし) 氏 ( 関西大学 社会学部 教授 堺市人権施策推進審議会委員(会長))
0.差別が生じるメカニズム
典型的な差別は、とあるカテゴリーの人たちをこういうやつだと決めつけて、遠ざけたり見下したり排除したりして不利益を与えることだ。世の中の当たり前はマジョリティに合わせて作られているために、よくわからない存在だとみなされるマイノリティの人たちを排除する傾向がある。また、無意識/無自覚になされる差別もあるし、差別されている人たちがいるにも関わらずその存在や経験を無視したり、それらを容認してしまう社会のしくみがある。差別は「する」「しない」だけではなく、意図せずとも発生する、社会環境の中に「ある」ものなのである。
1. 部落問題とは何か?
① 被差別部落とは?
部落問題の前提として、被差別部落の存在がある。そのルーツのひとつは中世で、この時代に死穢・産穢などの穢れが法制化された。穢れを取り扱えるのは当時特殊な技能を持つとされた人々だが、時代が進むにつれて徐々に穢れているとみなされるようになり、江戸時代に「穢多・非人」等の身分として固定化された。しかし必ずしも最下層ではなく、平人とは別・外に置かれる存在だった。皮革産業などを独占したり、犯罪を取り締まるなど、社会の中で特定の役割を果たしていた。
ところが近代に入り太政官布告「解放令」(1871年)が公布されると、役負担の解除と権利の剥奪が起こる。特定の職業に就いていた穢多・非人の人々が仕事を失い、穢れ意識にもとづく差別と貧困の連鎖が生じ、多くの被差別部落が次第に困窮していった。
② 同和地区とは?
差別を撤廃するために、行政施策の対象として指定された地区のことを同和地区といい、1993年段階で4442地区(216万人)あった。西日本(近畿以西)に地区・人口が多いので問題が可視化されやすく、社会運動や行政施策に結びつき、部落差別の撤廃を目指す同和教育も進展した。
③ 部落差別とは?
差別の定義は冒頭で話した通りだが、部落に居住する人々、そこにルーツを持つ人々に対して日常生活、結婚、就職などの場面において差別が引き起こされてきた。関わってなんらかの差別や問題に巻き込まれても困るという認識で、被差別部落やそれに関係する人々を避けようとすることも結果的に差別を生み出す。
④ 部落問題とは?
国の動きとしては1965年に同和対策審議会答申が出された。69年には同和対策事業特別措置法が制定され、同和地区として指定された地域や、居住する人々に対する差別をなくすための予算措置がなされた。以降、生活環境の改善、社会福祉および公衆衛生の向上と増進、学校教育および社会教育の充実など、さまざまな施策が実行された。その結果、地区の住環境は大きく改善し、同和教育や市民啓発によって部落差別はなくすべきだとする認識と理解が広がった。
その一方で施策に対する「不公平」「逆差別」「同和利権」という非難の声が上がるなど、社会的に解決されるべき問題にもかかわらず自己責任・部落責任論が一定の割合で支持されている。こうした声が出るのは人種差別や性差別に対する施策においても同様であり、差別問題の解決を難しくさせている。
2. 部落差別の現在
① 情報化による部落差別の拡散・拡大
差別意識は100年前と比べ大きく改善されたが、結婚差別、差別発言、身元調べなどがなくなったわけではない。特にインターネット上での部落への偏見、差別扇動、身元暴きなどが近年の大きな課題だ。不安を煽る情報は伝播しやすく、ネット上で被差別部落に対するネガティブなイメージが拡散されている。部落問題に見られる典型的なイメージは、怖い人がいて優遇を受けていてずるい、だまっとけ=寝た子を起こすな(この問題に触れない方がいい)だ。
どこが部落かを暴くネット上の動きもあり、2016年には「全国部落調査」復刻版出版事件が起きた。1975年には被差別部落の地名リストである「部落地名総鑑」を多くの企業が購入していた事件が発覚し、就職時の身元調査に悪用された過去もある。現在大阪では探偵・興信所による同和地区情報の調査などを規制する条例(1985年)があり、調べる行為は禁じられている。出版事件を起こした同じ人達は、ユーチューブで「部落探訪」という動画も発信していた。これはネット署名により削除されたが、被差別部落を勝手にさらす情報は後を絶たない。
このようにネット上での差別が無視できない状況になり、部落差別解消推進法ができた(2016年)。他方で学習経験が減った影響で、若い人ほど部落差別について知識がなく、若年層では不当な差別だと認識している人も半数を切っている。つまり最もネットを使う世代が誤った情報に騙されやすいので、あらためて学校教育などで対応してく必要がある。
② 部落差別解消推進法の成立
差別意識についての調査では、結婚時に同和地区出身者かどうかを気にする人は主に年配の人だ。一方で住宅を選ぶ時の被差別部落への忌避意識は年代問わずかなり強く、半数の人が避けるというデータもある。治安が悪い、怖い、同じようにみなされたくないなどがその理由だ。マイナスイメージを今後いかに払拭していくかが課題だが、そういう意味では各種メディアの役割は大きい。2016年の部落差別解消推進法以降、特集を組むなどして部落差別の現実、さらにはそれを乗り越えようとする営みが報道されることも増えたが、日常生活で話題になることは少ない。
3. 部落問題のこれから
「こわい」「ずるい」というのは偏見で、部落の人たちは過度に一般化されたイメージで語られている。また「だまっとけ=寝た子を起こすな」は、差別に直面しても相談すらできない状況を生む。適切な情報がなければ、多数派にとっては「寝た子を起こすな」になってしまう。なぜそうなるかというと、差別を知ることと差別をすることを混同しているからだ。マイクロアグレッションやアンコンシャス・バイアスも含め、差別を見抜くためには、まずは差別がどういうものかを学ぶ必要がある。差別とは人から人にうつるウイルスのようなもの。差別を跳ね返すためには予防接種的な差別問題学習が必要であり、しっかりとした人権認識は、免疫の役割を果たすだろう。